2025年4月13日から10月13日の184日間、大阪の夢洲を舞台に開催された「大阪・関西万博」。株式会社人間は、万博会場の装飾プロジェクト『OPEN DESIGN 2025「EXPO WORLDs」』のプロデュースから企画・制作や広報・PRまで担当しました。このプロジェクトは、ビジュアルとサウンドの両面で夢洲会場全体を彩るというものです。このチームには、会場デザインプロデューサーを務めた建築家の藤本壮介さんや、デザインシステムを手掛けたクリエイティブディレクターの引地耕太さんも参画。合計32組のアーティストに加え、約100人の協力者たちと共に万博が目指す世界観を体現しました。
今回は、10月12日に大阪府立江之子島文化芸術創造センター(enoco)で開催した「大阪・関西万博デザイン展」のトークイベントをダイジェストでお届けします。当日は、花岡がファシリテーターとなり、藤本さん、引地さんの3名で90分間のトークセッションを実施。プロジェクトが発足した経緯から、苦労話や裏話も……万博閉幕前日と言うタイミングで明かされた、それぞれの本音とは?
藤本壮介(ふじもとそうすけ)
建築家/大阪・関西万博 会場デザインプロデューサー
東京大学工学部建築学科卒業後、2000年に藤本壮介建築設計事務所を設立。主な作品は、ブダペストのHouse of Music、白井屋ホテル、ロンドンのサーペンタイン・ギャラリー・パビリオン2013など。2024年には「(仮称)国際センター駅北地区複合施設基本設計業務委託」の基本設計者に特定。
引地耕太(ひきちこうた)
東京/福岡を拠点に活動。2025年株式会社VISIONsを設立。これまでに大阪・関西万博のデザインシステムをはじめ、万博夢洲会場のデザイン・アート・サウンドによるオープンデザインプロジェクト『EXPO WORLDs』をはじめ、東京五輪や大阪・関西万博、紅白歌合戦といった国家プロジェクトのクリエイティブから、NIKEやYANMARなど数々のグローバルブランドのクリエイティブ、スタートアップのデザイン戦略に至るまでその活動の幅を広げている。
「切羽詰まった状態」で始まったEXPO WORLDsプロジェクト
花岡:
もうすぐ万博が終わります。まず、藤本さんはどうご覧になっていますか?
藤本:
本当に素晴らしいですよね。僕らは開幕前からデザインをしてきたわけですが、実際は、来場者やスタッフのみなさんがその場に来るまで、どうなるか全く分からない。それが開幕日には、わっと人が入ってきて、みんな楽しそうな顔をしていた。大屋根リングの上でも人が歩いていて……という景色を想像はしていたけど、それをはるかに超えて「命がもたらされた」と感じました。そこからさらに盛り上がり、終盤を迎えています。万博って、やっぱり最後は人の力でつくられるものなんだな、と思っています。引地さんはSNSでの“煽り”もすごく上手でしたよね。
花岡:
煽りですか?
藤本:
なんというか、いやらしさがないんですよ。見ている人を刺激はするんですけど、力加減がうまくて。その振れ幅を大きくしていきながら、どんどん人を巻き込んでいく様子は、すごく印象的でした。こういう発信って、調子に乗ってる感じが出てしまうとダメなんですよね。セーフとアウトの境界を見極めながら、上手にコミュニケーションを取っているなと思っています。

花岡:
本当にそうですよね。僕には絶対無理なんです。SNSの話はこのあとじっくり聞かせてもらいたいので、まずはEXPO WORLDsを振り返っていきましょう。
引地:
そうですね。まずEXPO WORLDsは、夢洲の万博会場を装飾する「会場ドレッシング」と、夢洲の万博会場を包み込む「会場サウンドスケープ」で構成されています。モニュメントや撮影スポット、こみゃくをモチーフにしたサインは、ドレッシングに含まれます。25組のアーティストに制作してもらった壁画などのアート作品も、このプロジェクトによるものです。
花岡:
まだ建物が出来上がっていない段階から、壁画を描ける壁を探しましたよね。
引地:
壁ハントやりましたね! あれも大変だった(笑)そしてサウンドスケープは、会場内をエリア分けし、それぞれ異なるBGMを作る企画。こちらは7人のアーティストと共創していきました。
花岡:
僕らはEXPO WORLDsで声をかけてもらったのがきっかけで、藤本さんと深く関わるようになったんですよね。
引地:
そうですね。装飾と音楽を使って、会場デザインプロデューサーとしての藤本さんの考え方を実装するプロジェクト、と表すこともできるかもしれません。
藤本:
実は初めにお声がけしたときには、すでにだいぶ切羽詰まった状況でした。会場では工事が始まり、だんだん出来上がってきたときに「あれ?」と気づいて……。万博会場には建物があって、樹木やベンチなどのランドスケープがあって、あれ? それだけで大丈夫なんだっけ? バナーやサインのような、細かい要素が要るよな、と気づいたんです。早く気づけよって話なんですけど……。
花岡:
忘れてたんですか!?
引地:
(笑)具体的なブランディングや、装飾周りを同時並行できないくらい大変だったということですよね。
藤本:
会場デザインにまつわることは、僕が全責任を持つわけですが、ここから誰の力を借りよう? と考えたときに、機動力があって地元ベースでいろんな展開をしてくれそうなのは、株式会社人間だと思ったんです。ご縁があり、つないでもらったのですが、かなりのキャラだと身構えていました(笑)もうそのときには、引地さんとお仕事をされていたんですっけ?
引地:
いえ、実は僕らが出会ったのは、藤本さんとご一緒する直前だったんですよね。
花岡:
引地さんはトップレベルのクリエイティブディレクター。「大規模な国家プロジェクトの一部を任されるとなったら、やっぱり強固なチームを作りたい」と思ってお誘いしました。このプロジェクトが始まったのが2024年の春なので、ほぼ1年でなんとかした、ということですね。

顔はめパネル、巨大バルーンも!? 100案の企画を絞り出し、取捨選択した
藤本:
僕はその分野に明るくなく、何を作ればいいのか考えるところからお願いしました。
引地:
あのころは要件も決まっていませんでしたよね。でも、そこまで任せてもらえるのは嬉しかったですよ。本当にゼロベースで「どうやったらワクワクさせられるか」「万博全体のコンセプトを実現するために、こういう打ち手があるんじゃないか」と考えて、膨大な量の企画を出しましたよね。
花岡:
キックオフのころは約20人くらいのチームを作って、工事中の万博会場に入って視察をしました。あのときは100案くらい企画を考えました。それで、藤本さんに1時間だけいただいてオンラインでプレゼンしましたよね。聞くのも大変だったと思いますが、あのときどう思われましたか?
藤本:
この人たちにお願いして本当によかった、というのと、全部実現できたらいいなと思いました。
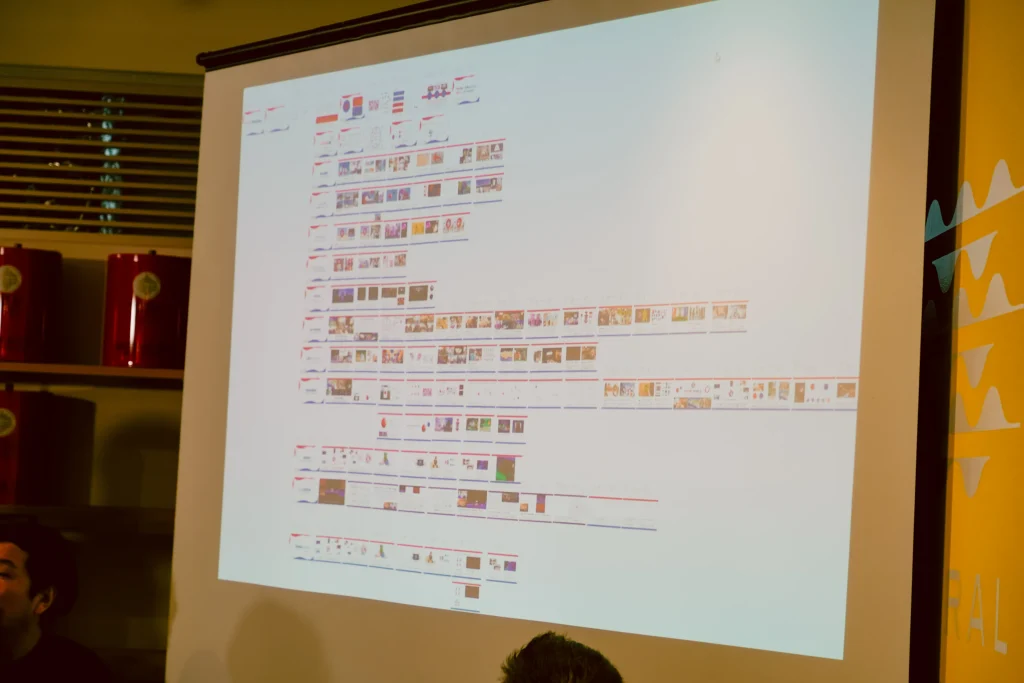
提案した100個の企画
引地:
僕らもまさか「全部やりたい」と言われるとは思っていなかったので、マジですか!? ってなりましたよね(笑)本当にいろんなアイデアがありました。大屋根リングの上を公園にして、アートなどを置く案でした。それから、バルーンを作るっていう案もありましたよね。全長50メートルのミャクミャクのバルーン、夢洲に立たせたかったな。
花岡:
僕がやりたかったのは、半年の会期中、毎日ずっと誰かがリングを走る「いのちのバトンリレー」という企画。1周2キロのリングでバトンを受け渡しながら会期中走り続ければ、計算上では地球半周分くらいの距離になるんですよ。それから、公開ラジオブースも実現させたかった。屋台みたいな形で出現させて、お客さんやクリエイター、万博スタッフの声を拾っていくようなアイデアでした。もしできていたら、みんな聞いてくれたと思うんやけど。そういえば藤本さんは、やたら「顔はめパネルを作りたい」と仰ってましたけど……。
引地:
僕も気になってた。あれだけいろんなものをきれいに作り込んでいるプロデューサーが、なんで顔はめにこだわっているんだ? って僕らはすごい悩んでたんですよ!(笑)
藤本:
いや、なんでですかね……顔はめって、なんかいいじゃないですか(笑)
引地&花岡:
えぇっ(笑)
藤本:
顔はめがあったら絶対写真を撮りたくなるだろうなと、そんな光景が浮かんだんです。
引地:
でも実際に今あったら人気になってたかもしれませんね。ようやく答えが聞けたけど、分かったような分からないような……(笑)そこから、限られた予算やさまざまな条件と照らし合わせて、案を絞っていったんですよね。

誠実に説明し尽くすスタンスで、SNSを味方にした
花岡:
先ほども少し話題が出ましたが、SNSについても聞いてみたいと思います。今回の万博は「SNS万博」ともいわれています。藤本さんは、開幕のかなり前からXで戦ってこられましたが、そもそも、なぜ藤本さんはSNSで万博の意義を伝えようとしたんでしょうか?
藤本:
万博のプロデューサーの打診を受けたときの話に戻るのですが、そのときは「なかなか大変な仕事だろうな」と思いました。ちょうど2020年の春で、オリンピックの建築、ロゴ、開会式に関する問題を間近で見ていたころです。だから「国家プロジェクトに関わると、建築家生命が絶たれるのではないか」という考えすらあった。
引地:
藤本さんですら、そう思ったんですね。
藤本:
どうしようかなと思ったけど「やらない選択肢はないよな」という結論に至りました。1970年の大阪万博で建築家・丹下健三さんが務めたプロデューサー業を、いま自分に任せてもらえるなんて、まずありがたいことです。そして、巨大プロジェクトのど真ん中にいるか、それとも外にいるかと問われたら「もうこれは中に行くしかない」と。当事者としてもがきながら、何かを作る方が面白いと思ってしまったんです。クリエイターとしては、もうやるしかない。
花岡:
腹をくくった、ということですね。
藤本:
ただ、万博というものが意義深いものでないのなら、そこに巻き込まれるのはよくないな、とも思いました。そこで、少なくとも自分なりに心底納得できるよう、意義について考えるようになったんです。今の時代の万博ってなんだろう? と考えたとき、結局は「たくさんの国が集まって、ひとつの場所に一緒にいる」という、万博のフォーマットそのものに一番価値があるのでは、と思い至って。テーマやコンテンツを載せる、その下にくるピザ生地みたいな部分がすごいんじゃないかと。
引地:
だからこそ、建築家としての生命を懸けて引き受けた。
藤本:
打診を受けてから3、4か月はスケッチを描きながら、どんな会場がいいか考えていました。それで、夏に博覧会協会とプロデューサー陣にプレゼンをしたら、賛同してもらえたんです。関西の財界のみなさんも、僕たちの案を歓迎してくださり、そのまま2020年の12月に記者発表を行いました。
藤本:
当初の建築予算を超えてしまったことを指摘する記事もありましたが、全体としては受け入れてもらえた感触でした。しかし、2022年にロシアのウクライナ侵攻が始まり、情勢が変わってきた。資材の高騰などで建築費用が膨れ上がったことなどが引き金になり、バッシングが一気に押し寄せてきたんです。「値段が上がったのは、どうやら藤本たちのせいらしい」といったことも言われるようになりました。いろんな意見があるのはいいことですが、誤解が誤解を呼んで、事実に基づかない情報で炎上するのは心外だなと。最初は個別の意見に対して対応・説明をしていたのですが、このままでは理解が進まないと感じてきて。
花岡:
そこから、あの「万博の意義」のポストが生まれたんですね。
1:万博の意義について、
会場デザインプロデューサーとして、僕自身が考える万博の意義について述べておきたい今回の万博については、1970年の大阪万博の時とはすでに時代が違う、21世紀になってまだ万博などやっているのか、万博などすでに時代遅れだ、という指摘がある。…
— Sou Fujimoto 藤本壮介 (@soufujimoto) January 27, 2024
藤本:
SNSから離れて、仕事を粛々と進めるという選択肢もあったんだけど、「これだけ素晴らしい万博なんだから、俺が説明してやる!」と思って(笑)協会の広報の仕事では? とも言われたけど、公式の組織に“翻訳”されるよりも「会場デザインを一番理解している自分の言葉で説明した方が、より伝わるんじゃないか」と考えたわけです。万博の意義、デザインや木造のこと、コストについても発信しましたが、やはり根底には、事実をちゃんと伝えたいという思いがありました。
引地:
でも、それをきっかけにさらに勘違いを呼んで炎上する、みたいな心配はなかったですか?
藤本:
ありましたよ。でも、是が非でも反対したい人は、何を書いても反対すると分かってきた。一方でニュートラル層には理解が広がっている感触があったんですよね。
引地:
発信された内容もさることながら、藤本さん自身の、逃げも隠れもしない姿勢に対して共感というか、信頼が広がっていったのかもしれませんね。
藤本:
どれだけ信念を持ってやっていても、反対意見は出てくるものです。そういう意見も一理あるよなと思いつつ、こちらとしては恥ずべきことは一切ないと、ちゃんと伝えたかったんですよね。それで、説明し尽くすというスタンスをとりました。
花岡:
そのスタンスには、引地さんは特に感化されてますよね。
引地:
そうですね。藤本さんに勇気づけられて発信を続けてきた部分があります。今回のデザインシステムは「開かれたデザイン」というコンセプトがあって、プロセスやナレッジを共有することで、これまでの閉塞感を打開したい思いもあったんですよね。それでも心が折れそうになったときに、藤本さんがいてくれた。この規模の国家プロジェクトで、クリエイターが個人として発信し続けたのは革命的な出来事だったとすら思っています。
藤本:
オフィシャルの発信だけでは、きっと抜け落ちてしまう部分があるんですよね。協会も半ば例外措置として、僕の活動を許容してくれた部分はあるのですが、この動きがポジティブな前例になってくれたらいいなと思っています。
花岡:
藤本さんだけでなく、若手建築家の発信も顕著でしたよね。個人が発信することの大切さに改めて気付かされました。
藤本:
プロデューサー層だけではなく、若手のクリエイターも発言できるようにも働きかけました。あと、落合陽一さんが僕ら以上に自由に発信されていたのが、結果的には巨大な盾になってくれた(笑)彼が実際はどう考えていたのかは分かりませんが、バランス感覚が相当優れたクリエイターです。自らも傷つきながら、僕らを守ってくれていたんですよ。
引地:
そういったアクションもあり、最終的にはSNSによるポジティブな変化も見られたというのが、この万博の大きな流れでしたね。

二項対立の隙間にある「あわい」が見えてきた
花岡:
国家プロジェクトを含め、これからのビッグプロジェクトの在り方についても考えたいなと思います。このトークイベントもそうですが、公式と非公式の間でやってる感じがして。「国家と市民」「組織と個人」「夢洲とまち」と、それぞれの間について考える万博でした。それらの間をつなぐものが、組織なのかプラットフォームなのかを考えている途中なんですけど、現段階では僕らは「あわい」と表現しています。
引地:
こみゃくも会場マップも二次創作がどんどん生まれました。与えられたものの足りない部分を、SNSなどを使ってみんなで補っていったんですよね。トップダウンとボトムアップの中間にある「あわい」が立ち上がった万博だったと思います。藤本さんはどうですか?

藤本:
大きなプロジェクトだから、協会のような組織がないと物事は動かない。でもその組織がガチガチだと、面白いことは起きづらいんですよね。今回よかったなと思うのは、僕から見ると、協会がまあまあゆるかったこと。僕の発信やほかの二次創作に目くじらを立てることをしませんでした。これからの運営組織は、組織体としてはきちんと作られながら、ある種のバッファを持って緩やかに判断を下していくことができれば、面白いものを生み出せるんじゃないですかね。
引地:
来場者の過ごし方も自由でした。
藤本:
リングの下では小学生がシートを敷いてお弁当を食べたりね。組織の在り方によっては禁止されてもおかしくないのに、ある程度の裁量の中で、いろんなことを柔軟に判断してきた。だからこそ、あのお祭りみたいなダイナミズムや印象的な風景が生まれたのだと思っています。組織と個人どちらかがいいという話ではなくて、曖昧なところを組織として許していくこと——人間的な要素を取り込んだ組織が必要です。その作り方のヒントが見えた万博でした。
花岡:
例えば、行政もリソースが減って民営化が進む中で、その中間組織みたいなものが必要になってくるんじゃないかと思うんです。大企業でもそうかもしれません。大きな組織の中を横串的に横断するチームが必要だと思っていて、今後はそれに名前を付けていきたいと考えています。
引地:
特に行政は隅々まできっちり管理するためのリソースがなくなっていきます。そこをゆるく統制することで、市民が楽しみながら補う構造ができたらいいですよね。みんなが自分ごと化できるような、関わりしろをデザインしていくことで、一人ひとりの「いのちかがやく」につながっていく気がします。
藤本:
行政だけが「あれもこれもやらなきゃ」と枠を作るのではなく、余白を作ることで、みなさんが楽しみながら参加できるシステムになっていくといいですね。
大阪ならではの「面白がり力」が未来社会のヒントに?
花岡:
最後に、大阪についても聞いてみたいです。僕は大阪生まれで仕事も大阪でやってきました。今回の万博って、大阪だからこんなに盛り上がったんじゃないか、大阪だからあのゆるさ、あわいができたんじゃないかと思っています。大阪人の「面白がり力」について、藤本さんはどう思われますか?
藤本:
面白がり力、強すぎますよね(笑)僕は海外でも仕事をしていますが、大阪人はラテンの人たちに似ているなと感じます。人間主体で関係を築いていって、組織化する土壌がある。大阪のキャラクターがあったから万博がうまくいったよと、世界にもっと発信したいです。人が人を巻き込んで、勝手に盛り上がっていく、共鳴していくのが「大阪モデル」だと実感しました。
花岡:
まさに大阪モデルですね。1970年の大阪万博はハードレガシーが多く残りましたが、今回はソフトレガシーが大阪に残って、人がつながり、うねりになってほしい。どうしても企業の本社は東京に多くて、大阪は経済的にも閉塞感がある。この万博で、自分たち自身のユニークさに気付いて、誇りを取り戻す機会になればいいなと思います。
藤本:
同じものを見ても、それを面白がれるか文句を言うかで、未来は変わってくる。面白がることができれば、面白さはさらに広がっていくことが証明された。これを広めたいですよね。

文:山瀬龍一
写真:はまだみか(人間)
